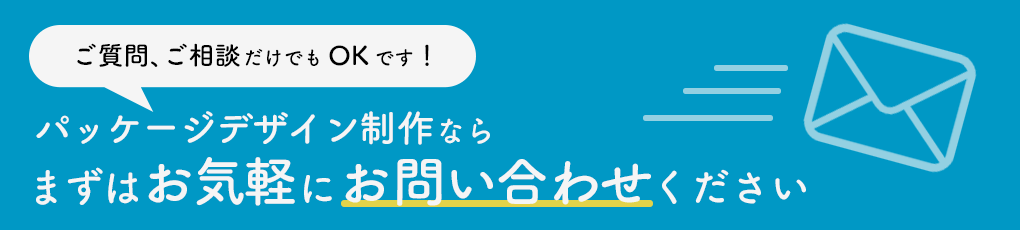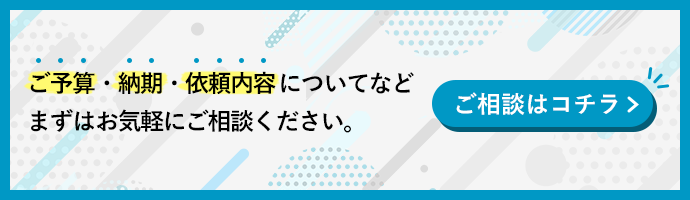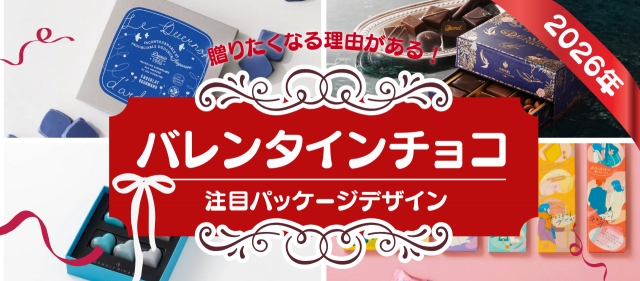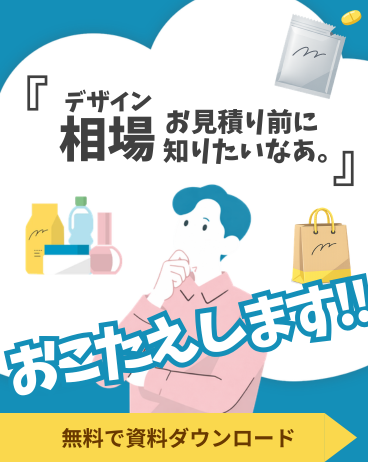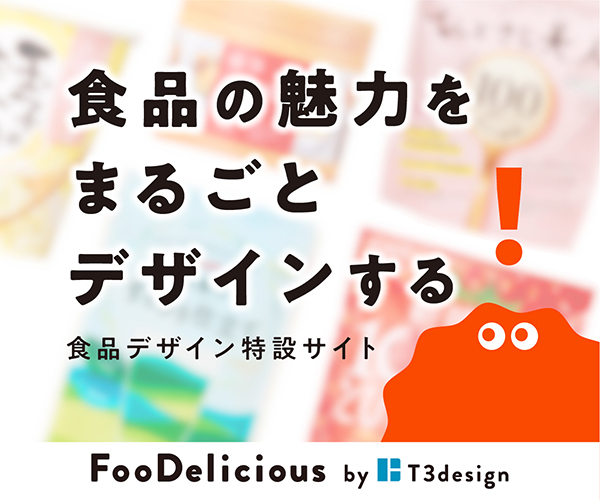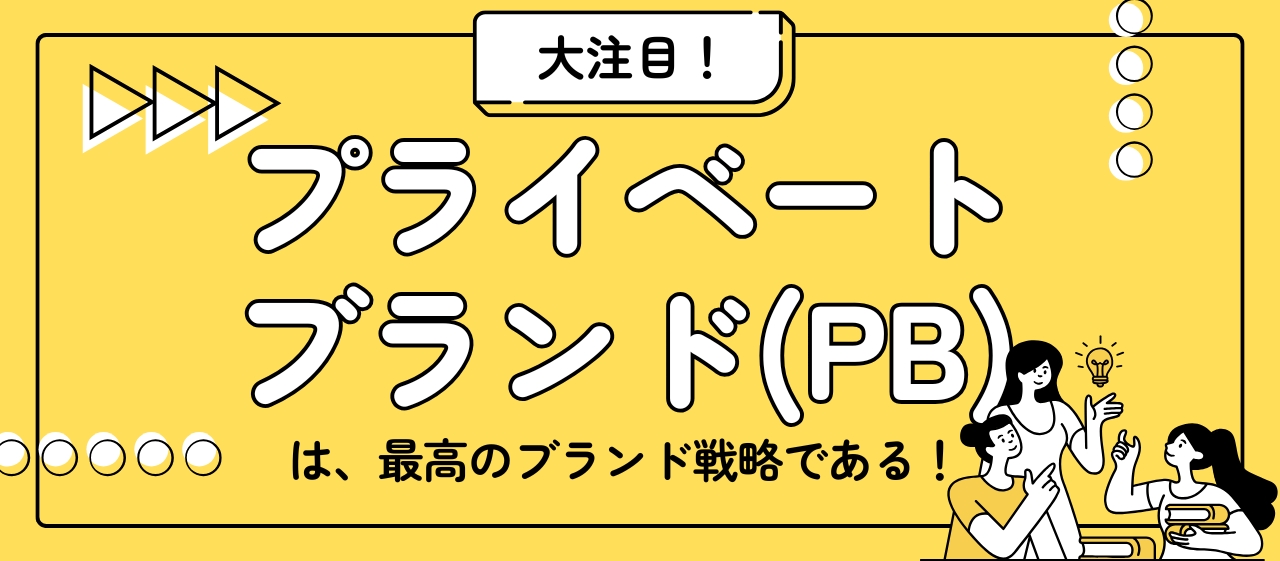
こんにちは、広報部長です!
コンビニで、スーパーで、プライベートブランド(PB)商品がよく目につきます。見た目に統一感があるので何となく視認しやすく、しかもお安い。大手メーカーの打ち出すナショナルブランドは当然、安定の信頼感ですが、この物価高、ついついPBに手が伸びてしまいます。
今回は、そんなプライベートブランド(PB)についてのお話。実は今、ものすごく注目を浴びているんですよ!
1. プライベートブランド(PB)の魅力
1-1.プライベートブランドって何?

プライベートブランド(PB)というのは、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの小売業者が自社で企画・販売するブランド商品を指します。この場合、中身そのものの製造はメーカーに委託することが多いようですね。
「プライベート(自分たちの)ブランド」ですから、価格を比較的安価に設定することができて、デザインや仕入れ数なども自分たちでコントロールできるところが魅力。もちろん自分のお店ですから、どーんと大きな売り場を構えてもOKというわけです。
ちなみにプライベートブランドの対局にあるのが「ナショナルブランド(NB」。全国規模で流通しているメーカー主導のブランド商品のことです。キリンのビールや明治のチョコレートなどが代表例ですね。
ビールならビールメーカー、チョコレートならチョコレートメーカーが企画・販売・広告展開を行っていて、小売店はそれを仕入れて販売するというわけです。パッケージや広告、価格などを小売店側が大きくいじることはできません。
全国展開している商品ですから、基本的にはどこでも同じ品質で同じ価格(オープン価格になっている場合もあります)。メーカーさんの広告はとにかく大きく宣伝費をかけますから、CMや駅貼りのポスターなどプロモーションも大々的で派手。もちろん認知度もそれだけ高くなりますね。
1-2. なぜプライベートブランドを作るの?
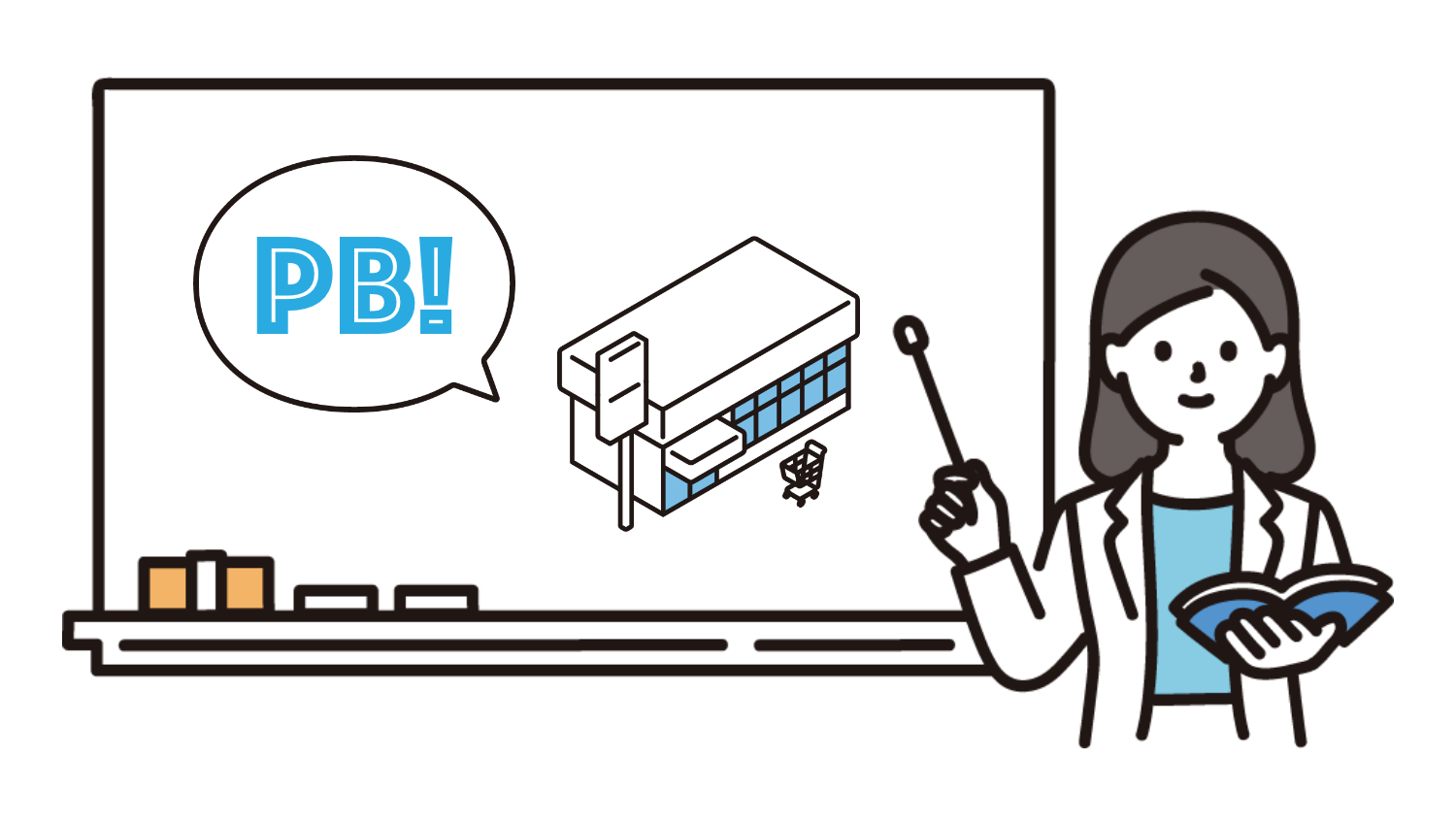
利益率が高い!
PBの最大のメリットは、利益率です。NB商品は小売店の店頭に並ぶまでにさまざまな中間マージンが乗ってきますが、PBは自社商品のためそこのコストをカットすることができるんです。原価を抑える、開発費用の無駄をカットするなど、利益全体に関わるコントロールがしやすいのが嬉しいところです。
他社との差別化ができる!
「安いけど品質もそこそこいいぞ」というPB商品は、ユーザーの来店動機や購入動機につながります。そんなふうに価格で他社と勝負しつつ、独自の「良さ」や「世界観」を打ち出すことができれば、さらにファンがついてくれることになりそうですね。
ブランド戦略の一環になる!
PBを作ることで、お店や企業の世界観・価値観を表現することができます。
NB商品はどこのお店に並んでも同じ商品。そこに独自の世界観を持ったPB商品を展開することで、お店の「顔」を作ることができるということです。ここにはデザインが大きく関わってきますよね!
消費者との関係が密になる!
自分たちで自分たちのブランドの商品開発をしているということは、店頭で受け取ったユーザーの声やニーズに即対応できるということです。フットワーク軽くブランドをブラッシュアップさせることができれば、ユーザーとの信頼関係はさらに密に。自社店舗でマーケティングができるというのもかなりの強みです。
こんなふうに、PBを展開することにはメリットがたくさんあるんです。この良さに気付いた小売店業界では、今PBを次々立ち上げ、どんどんブラッシュアップさせるという、ちょっとしたムーブメントが起きています!
1-3. プライベートブランド、どうデザインする?

PBを立ち上げるのは小売店にとってメリットだらけ。そしてそれをより強化するためには、デザインが「いい仕事」することが必要不可欠です。ではここで、どうデザインすればPBが盛り上がるのか、考えてみたいと思います。
ブランドの世界観に完全に寄せて「良さ」を作り出す!
PBは「そのお店の顔」。統一感がとにかく命!です。
例えばPBの最大手「無印良品」は、その極限まで削ぎ落としたシンプルデザインと独特のカラーコードで「どこからどう見ても無印」を成功させていますよね?
そのように、見た瞬間に「この店っぽい!」と思わせる強いビジュアルが必要なんです。
NBと並べたときに「迷わず選べる」わかりやすさが鍵
NBはロゴとビジュアル、ブランド力で勝負しています。そこにいくらPBが挑もうとしても太刀打ちできません。ではどうしましょう。そこで打ち出したいのは市民の生活に寄り添った誠実さです。「実用性・安心感・わかりやすさ」で勝負するのがセオリーと言えます。
例えば、商品名・内容物・容量・価格感がひと目で伝わるように。過度な装飾はえて避けて、フラットなデザインやシンプルなアイコン表現を活用。パッケージは、棚に並んだときに「情報の見やすさ」が命となります。機能や価値が一瞬で伝わる「視認性」を前面に打ち出すのが勝負の鍵です。
訴求は「さりげなく」。生活になじむ「余白と整頓」の美学を
特にインテリアにもこだわりたい若い世代は、生活感に馴染むデザインを選ぶ傾向にあります。家に置いてもださくない、インテリアを邪魔しないデザインこそがリピート購入につながります。「飾らないけどおしゃれ」を狙いましょう。
また、サステナビリティな健康訴求も大切な鍵。「無添加」「低糖質」「環境配慮素材」などの要素をさりげなくデザインに溶け込ませるのもとっても大切なポイントです。アイコンやピクトグラムを活用したいところですね。
意識の高さはあるけどうるさくない、邪魔じゃない、説教くさくない、このバランス感覚が大事です。
2.みんな知ってる?有名「PB」デザイン集
2-1. 無印良品

自社企画商品すべてがPBと言える、PB界の最大手。
言わずもがなのシンプルデザインですが、究極のシンプルが「無印良品そのもの」となっているものすごい例です。
1980年に消費社会へのアンチテーゼとして生まれた無印良品。「無印」という立場に「良品」という価値観をつけた概念を誕生させました。20世紀の日本のグラフィックデザイン界を代表するデザイナー・田中一光氏を初代のアートディレクターに迎え、その思想を体現する世界観を確立。田中一光氏没後は原研哉氏がディレクションを引き継いでいます。
2-2. セブンプレミアム(セブン&アイ)

既に2000年代に始まっていたセブンプレミアム。総アイテム数49という小規模でのスタートでした。「ジェネリックNB」「廉価版」のように捉えられがちだったPBのイメージを払拭すべく、おいしさ、安全・安心などの面で独自の高いクオリティを生み出し、しかも価格競争力を持つ商品という考え方を商品づくりの基本に据えていました。
ブランドとしてビジュアルの統一をはかったのはブランドが走り出してから少し後のこと。ディレクションは佐藤可士和がつとめています。カテゴリーを整理し、デザインフォーマットを作成し、すべてのオリジナル商品にロゴをつけることで、店内でのPBの存在感が一気に増し、ブランドが際立つことになりました。
2-3. トップバリュ(イオン)

「お客さま第一」のイオンPB「トップバリュ」。シンプルながら目立つ色使いと形のロゴが、遠くからでも「トップバリュだ!」と分かる絶妙な視認性を確立しています。
トップバリュの強みはそのパッケージ表記です。アレルゲンや栄養成分など、ユーザーが商品を購入する際に知りたいと感じている情報を、ユーザーの声を聞きながらわかりやすく表示に反映させています。
ユーザーからの意見や問い合わせがくると、すぐに社内で検討し必要に応じてどんどんデザイン変更を行なっているという徹底ぶり。PBだからこそできることですね。
2-4. 三つ星ローソン(ローソン)

コンビニのPBと言えば、ローソン。ユニークなデザインで話題だったローソンのPBは、2025年にリニューアルされることが発表されました。現行の約95%の商品を「3つ星ローソン」のブランド名に統一し、10月までに順次刷新していくとのこと。
パッケージはわかりやすさを意識し、商品名は見やすい大きさと濃さの文字に変更。パッケージカラーは商品に合わせた識別しやすい色を使用し、アレルゲン表示は、パッケージ前面での記載に変更するそうです。
「タイパ」「コスパ」が叫ばれる昨今、PBはかなりニーズが高まっています。この機に乗じて、購入商品を決定する際にわかりやすいパッケージデザインにこだわることで、さらなる躍進が期待されます。
2-5. みなさまのお墨付き(西友)
西友の「みなさまのお墨付き」は、第三者機関による消費者テストで80%以上の賛同を得られたものだけが「合格」としてラインナップに加わることができるという、こだわりにこだわりぬいたブランドづくりが魅力。
シンボルとなる「◎」に明朝体のロゴも非常に印象的ですよね。何よりコンセプトがブランドネームやロゴマーク、パッケージデザインにわかりやすく反映されているところがお見事です。
ブランド自体が高い評価を得ていて、「ナショナルブランドに較べて、個性を出しにくいプライベートブランドにおいて、極めて明確なコンセプトを打ち出し、商品開発からパッケージデザイン、マーケティングまで一貫して実現している。」とされ、2013年にグッドデザイン賞を受賞しています。